「SIerとSESって、結局なにが違うの?」そんな疑問を持つあなたへ
「SIerとSESの違いがいまいちわからない…」
「IT業界に興味はあるけど、どっちを選べばいいの?」
未経験からエンジニアを目指す多くの人が、最初にぶつかるのがこの疑問です。
インターネットで調べても専門用語が多く、どれが自分に合うのか分かりにくい。
SNSでは「SESはやめとけ」といった言葉を見かけることもありますが、
それが本当に自分に合わないかどうかは、正しい情報を知るまでは判断できません。
でも、心配はいりません。
「SIer」と「SES」それぞれの特徴を理解し、自分の性格や理想の働き方に合わせて選ぶことができれば、誰でも自分らしいキャリアを築くことができます。
この記事では、
- SIerとSESの根本的な違い
- 向いている人のタイプ
- 自社開発・受託開発との違い
- 自分に合う働き方を見つけるコツ
を、未経験の方にもわかりやすく丁寧に解説していきます。
大切なのは、「どっちが良い・悪い」ではなく、
「どっちが自分に合っているか」を見極めること。
焦らず、自分のペースで理解を深めていきましょう。
SIerとは?特徴と働き方
SIerとは何か
「SIer(エスアイヤー)」とは、“System Integrator(システムインテグレーター)”の略称で、
企業や官公庁などのクライアントに対して、システムの設計・開発・運用を一括して請け負う会社のことを指します。
たとえば、銀行のオンラインバンキングシステムや、メーカーの在庫管理システムなど、
日常の業務を支える大規模なシステムを「企画から開発・運用」までトータルで担当します。
つまりSIerは、企業のIT基盤を裏側から支える“システムの総合プロデューサー”のような存在です。
主な仕事内容
SIerの仕事は、プロジェクトごとに大人数のチームを組んで進めるのが特徴です。
主な工程は以下の通りです。
- 要件定義・設計:クライアントの課題をヒアリングし、システムの全体像を設計
- 開発・テスト:設計に基づいてプログラムを作り、動作確認を行う
- 導入・運用保守:納品後もシステムを安定稼働させるため、保守や改善を担当
このように、上流工程(設計・企画)から下流工程(開発・テスト)まで幅広く携われるのが特徴です。
SIerで働くメリット
- 大規模案件に関われる:社会のインフラを支えるような重要システムに携われる
- 教育体制が整っている:新入社員研修やキャリアパス制度が充実しており、未経験でも学びやすい
- 上流工程の経験が積める:マネジメントスキルや顧客折衝など、将来につながるスキルが磨ける
SIerの課題・デメリット
- 開発現場から離れやすい:上流工程にシフトすると、コーディングに関わる機会が減る
- 意思決定のスピードが遅い:大企業ほど承認フローが多く、柔軟な動きが難しい
- 納期・コスト重視の文化:顧客との契約上、自由な開発スタイルを取りにくいこともある
向いている人の特徴
SIerに向いているのは、安定した環境でじっくりスキルを磨きたい人や、
チーム全体の動きを見ながらプロジェクトを進めるのが得意な人です。
特に、周囲とのコミュニケーションを大切にできる人や、
相手の要望を整理して形にしていくことにやりがいを感じる人にはぴったりの環境です。
技術だけでなく、計画性や調整力といった“ビジネス的な力”も発揮できるのがSIerの面白いところ。
将来的には、プロジェクトマネージャー(PM)やITコンサルタントなど、
より上流のキャリアを目指す人にも向いています。
SESとは?特徴と働き方
SESとは何か
「SES(エスイーエス)」とは、“System Engineering Service”の略で、
エンジニアが他社のプロジェクトに参加して技術支援を行う働き方を指します。
簡単に言うと、SES企業に所属するエンジニアが、クライアント企業(=常駐先)に出向いて、
システム開発や運用・保守などの業務を行う仕組みです。
SES企業はエンジニアのスキルや経験をもとに契約を結び、
「人材 × 技術力」でクライアントをサポートします。
主な仕事内容
SESエンジニアは、常駐先によって担当する業務が異なります。
- システム開発・運用保守:企業のプロジェクトに参加し、プログラミングやテストを担当
- インフラ構築・運用:サーバやネットワークの設定・監視・トラブル対応を行う
- 技術支援・改善提案:クライアントの課題を技術面からサポート
1つの現場が終われば次の案件に移ることもあり、さまざまな業界や開発現場を経験できるのが特徴です。
SESで働くメリット
- 幅広い経験が積める:多様な業界・技術・開発手法を学べるため、成長スピードが早い
- 人脈が広がる:常駐先ごとに新しいチームで働くため、業界のつながりが増える
- 柔軟なキャリア形成ができる:スキルを磨いて自社開発やフリーランスへのステップアップも可能
SESの課題・デメリット
- 常駐先によって環境が変わる:チーム文化や使用技術が毎回異なるため、慣れるまで時間がかかる
- プロジェクトの裁量が小さい:あくまで支援側の立場のため、仕様決定などには関わりにくい
- 会社帰属意識が薄れやすい:自社オフィスにいない期間が長く、孤立感を感じる人もいる
向いている人の特徴
SESに向いているのは、新しい環境にも柔軟に適応できるタイプの人です。
現場が変わるたびに、扱う技術や関わる人も変わります。
そのため、変化を前向きに受け止めて「どんな環境でも学び取ろう」と思える人ほど、活躍しやすい傾向があります。
また、開発経験を積みながらスキルを広げたい人、
自分の得意分野を見つけたい人にもおすすめの働き方です。
短期間で多くの現場を経験できるからこそ、“成長の早さ”が最大の魅力とも言えるでしょう。
SIerが「一つの大きなプロジェクトを腰を据えて支えるタイプ」なら、
SESは「現場ごとに多様な経験を重ねて成長するタイプ」。
どちらが上・下ということではなく、自分の性格や価値観に合うかどうかで選ぶのが大切です。
SIer・SES・自社開発・受託開発の違いを比較
それぞれの働き方を整理しよう
IT業界でよく耳にする「SIer」「SES」「自社開発」「受託開発」。
どれもエンジニアが関わる仕事ではありますが、“どこで・誰のために・どんな立場で働くか” が大きく異なります。
まずは、4つの特徴を一覧で比較してみましょう。
働き方の比較表
| 項目 | SIer | SES | 自社開発 | 受託開発 |
|---|---|---|---|---|
| 主な仕事の内容 | クライアント企業のシステムを企画〜運用まで一括請負 | 他社のプロジェクトに常駐して技術支援 | 自社サービスやプロダクトを開発・運用 | 他社から依頼された開発案件を社内で制作 |
| 働く場所 | クライアント先や自社 | 常駐先(クライアント企業) | 自社オフィス(リモートも多い) | 自社オフィス中心 |
| 開発の自由度 | 低い(顧客仕様に合わせる) | 案件により変動 | 高い(自社判断で改善できる) | 中程度(契約範囲内で対応) |
| キャリアの方向性 | PM・コンサル志向 | 技術経験を幅広く積む | プロダクト志向・技術探求型 | 顧客対応・柔軟性重視 |
| 向いている人 | 安定・マネジメント志向 | 現場経験・挑戦志向 | 創造・改善志向 | バランス型・顧客対応が得意 |
それぞれの特徴をもう少し詳しく見る
● 自社開発
自社でWebサービスやアプリを開発する企業。
自分たちのアイデアを形にし、ユーザーの反応を直接感じられるのが魅力です。
開発の自由度が高く、エンジニアの意見が反映されやすい環境ですが、
成果への責任も大きく、スピード感が求められます。
● 受託開発
クライアントから依頼を受け、納期や仕様に合わせてシステムを作るスタイル。
さまざまな業種・要望に対応する柔軟性が求められ、コミュニケーション力も重要です。
自社で開発を行うため、チーム連携や社内ノウハウの共有がしやすい点がメリット。
「どれが一番いいか」ではなく「どれが自分に合うか」
SIerもSESも自社開発も受託開発も、それぞれに強みと課題があります。
「SESはやめとけ」「SIerは古い」といった意見を見かけることもありますが、
本質的には、自分がどんな働き方をしたいかで選ぶべきものです。
- 安定性を重視したいなら → SIer
- 現場経験を積んでスキルを広げたいなら → SES
- 自分のアイデアを形にしたいなら → 自社開発
- いろんな業界・技術に関わりたいなら → 受託開発
どの道にも、エンジニアとして成長できるチャンスがあります。
大切なのは、“他人の意見”ではなく、“自分の理想の働き方”を軸に選ぶことです。
自分に合う働き方の見つけ方 – 未経験からのステップ
自分に合う働き方を見つける3ステップ
IT業界にはいろんな道がありすぎて、最初は「どれを選べばいいの?」と迷うのが当たり前です。そんなときは、“自分の価値観”と“学びの方向性”から考えるのがおすすめです。
STEP1:自分の価値観を整理する
まずは、自分がどんな働き方に魅力を感じるのかを言語化してみましょう。
安定した環境で成長したいのか
いろんな現場を経験してスキルを磨きたいのか
自分のアイデアを形にする仕事がしたいのか
自分の“理想の働き方”を明確にすることで、SIer・SES・自社開発などの選択肢が自然と絞れていきます。どれが正解ではなく、「どれが自分にフィットするか」が大切です。
STEP2:現場で得たい経験を考える
エンジニアとして「どんな経験を積みたいか」を意識すると、キャリアの方向性が見えます。
- チームマネジメントを学びたい → SIer
- 現場の多様な技術に触れたい → SES
- プロダクトを作り込みたい → 自社開発
- 顧客の課題解決に関わりたい → 受託開発
自分が“得意を伸ばしたい”のか、“幅を広げたい”のかで選ぶ道も変わります。
STEP3:学習と実践を通して確かめる
どんな働き方が合うかは、実際に手を動かしてみないとわからない部分も多いです。
未経験のうちは、基礎を学びながら「開発体験」を積むことが一番の近道。
たとえば、スクールや学習プログラムでチーム開発を経験すれば、
自分がどんな作業にやりがいを感じるかがはっきり見えてきます。
学びの中で“自分の得意分野”を発見できれば、転職活動も自信を持って進められるはずです。
どんな働き方にも「正解」はない
SIer・SES・自社開発・受託開発、それぞれにメリットもデメリットもあります。
大事なのは、「どこで働くか」より「どう成長したいか」という視点を持つことです。
今の時代、キャリアは一度きりではありません。
最初にSESで現場経験を積み、その後SIerや自社開発に転職する人も多いですし、
経験を活かしてフリーランスとして独立する道もあります。
「今の自分に合う選択」をしながら、少しずつ理想の働き方に近づけていけば大丈夫。
焦らず、一歩ずつ進んでいきましょう。
違いを知ることは、“自分を知ること”につながる
SIerもSESも、自社開発や受託開発も――
どの働き方にも、それぞれの良さと難しさがあります。
「どっちがいい」「どっちが悪い」ではなく、
自分がどんな環境で、どんな働き方をしたいのかを考えることこそが、キャリアの第一歩です。
この記事のまとめ
- SIer:大規模案件を一括で請け負う安定型。マネジメント志向の人に向く
- SES:現場を渡り歩き、多様な経験を積む成長型。変化に強い人に向く
- 自社開発:自分たちのサービスを作る創造型。技術やアイデアを形にしたい人におすすめ
- 受託開発:さまざまな顧客の課題に応える柔軟型。コミュニケーション力が活かせる
働き方を選ぶというのは、
「自分がどんなエンジニアとして生きていきたいか」を選ぶということ。
今の時点で明確な答えがなくても大丈夫です。
知る・学ぶ・体験する──その繰り返しの中で、
少しずつ自分に合う働き方が見えてきます。
まずは一歩踏み出して、
“自分の理想のキャリア”を形にしていきましょう。

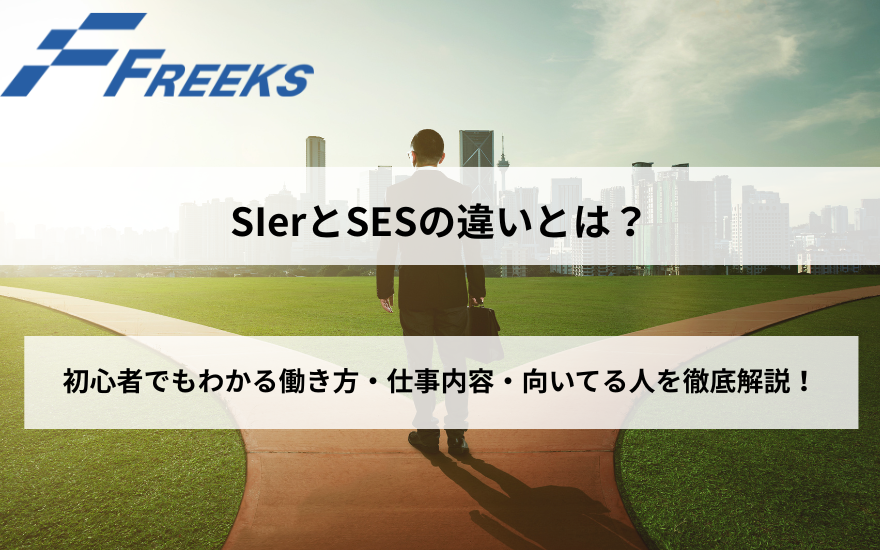
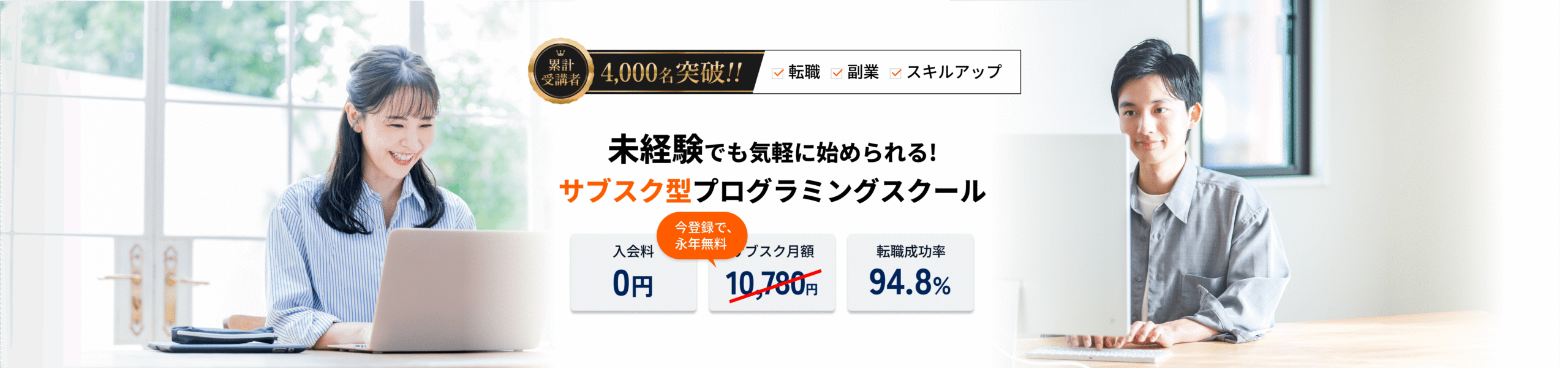
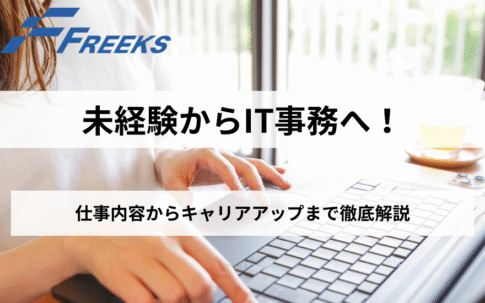


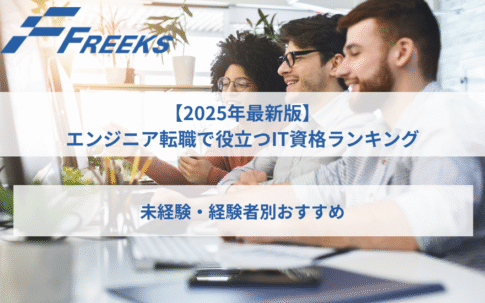

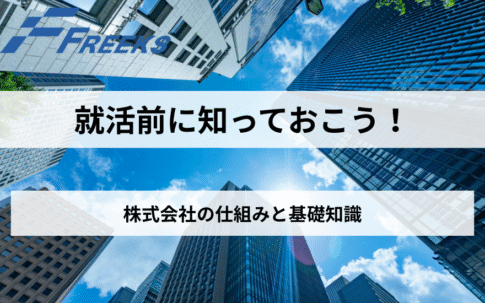







コメントを残す